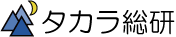タイトルを追加アフリカ人だらけの寮で7歳児が学んだ人種と世界
「ママ、何であの人たち、顔が焦げているの?」
7歳の息子が指をさした先には、音楽をかけて談笑している黒人男性たちがいた。私は思わず「しーっ」と自分の口に指をあてた。
実際のところ、息子は日本語で質問してきたので、彼らに聞こえていたとしても、意味は伝わらなかっただろう。けれど、私は息子の素朴な問いに虚を突かれ、彼の小さな手を引いて速足で彼らの前を通り過ぎた。
ちょうど10年前の2010年夏、私は12年勤めた会社を辞め、小1の息子を連れて中国・大連の大学院に博士留学した。
住まいは留学生寮の2人部屋。ビジネスホテルのツイン程度の広さで、トイレとシャワーはあったものの、お湯を溜めるタンクの容量は小さく、5分以内でシャワーを済ませないと冷水をかぶることになる。
キッチンと洗濯機は共用。中国人向けの寮に比べると設備は充実していたが、それまでの日本での生活との落差は大きかった。生活水準が著しく下がったと感じた息子は、「うち、お金ないの?」と何度も聞いてきた。
シングルマザーの私は、中国政府奨学金の審査にパスし、学費・住居費無料、生活費支給という待遇を得られたので、思い切った決断ができた。とはいえ支給される生活費は日本円にして数万円程度で、貯金を切り崩しながら切り詰めた生活を送ることとなった。
けれど私たちは、安定した収入と引き換えに、お金では買えないたくさんのことを学んだ。
大学には個室中心の寮と、2人部屋が前提の寮があった。自費留学生の大半が個室の寮を選んだため、私たち親子が住んでいた2人部屋ベースの寮の住民は、ほとんどが国費留学生だった。出身国の構成はベトナムやロシア、ラオスなど社会主義国が4割、アフリカが4割、韓国が1割で、私を含めたその他が1割だった。
当時、中国政府は留学生大幅増員プロジェクトを推進中で、留学先でも同じ年に入学した国費留学生が学部生から大学院生まで100人前後いた。
世界地図を手に留学生の部屋を回る息子

私たちの留学生寮には100人弱が暮らしていたが、長期で住んでいる日本人は他にいなかった。当時前歯が4本抜けて、笑うと周囲まで笑わされてしまう息子は、寮のアイドルになった。
クリスマスが近づくと、息子は日本語と中国語で「ここに子どもが住んでいます」と紙に書いて窓に貼った。外から紙を見た留学生仲間たちは、こっそりドアの外にプレゼントを置いてくれた。
夕食を食べると、息子はおもちゃやゲームを手に、留学生の部屋を訪ねた。どこの国の人であろうが、遊んでくれれば友達だった。
初対面で「顔が焦げている」ように見えた黒人とも、いつの間にか仲良くなっていた。冬はベトナム人グループが雪合戦に誘ってくれ、共用キッチンではアフリカの人々がダンスを教えてくれた。
そのうち息子は、世界地図を手に彼らの部屋を訪ねるようになった。地図を見て国の名前を答えることができても、それ以上のことをほとんど知らないと気付いたのは、他でもない親の私だった。
震災後、ラオス人学生が歌っていた日本の歌

アフリカからの留学生だらけの寮生活で、30代後半の私が交流を深められたのは、ひとえに息子のおかげだ。黒人の男性3、4人が共用キッチンで音楽を大音量でかけながら踊っていたとき、私はそこに近づくのを躊躇したが、息子は彼らとハイタッチして一緒に体を揺らした。
私たちの部屋には日本から持ち込んだ任天堂のゲーム端末があり、息子は留学生仲間を招き入れ一緒に遊んでいた。料理を作って部屋に戻ったら、大柄な黒人たちと息子がゲームで遊んでいて、1人は私のベッドで寝ていた、ということもあった。
息子がいなければ彼らは、正直「ちょっと近寄りがたい怖い人」のままだったかもしれない。
2011年3月11日、東日本大震災が起きた日。中国のテレビでも、津波の映像が繰り返し流された。息子は何が起こっているか分かっていなかったが、映像から伝わる恐怖感で泣いた。
その日の夜遅く、赤道ギニア人のミーシー、トルコ人のセレナ、韓国人の金夫妻が部屋を訪ねてきて、「家族は大丈夫か」と心配してくれた。「うちからは遠い場所だから家族は大丈夫……」と返事をするのが精いっぱいだった。
次の日も、その次の日も、寮内ですれ違う人々から「大丈夫か」と聞かれた。私の心は全く大丈夫ではなかった。そんなある日、部屋にいるとなぜか日本語の歌が聞こえてきた。
声をたどって行くと、ラオス人留学生が徳永英明のヒット曲「最後の言い訳」のサビの部分だけを繰り返し歌っていた。
「大事なものが遠くに行く、全てが思い出になる」というような歌詞の意味を分かって歌っているかはうかがい知れなかった。私は彼の歌声を震災に重ね合わせて涙を流し、同時に「カルチャーの広がり方って不思議だなあ」とも感じた。彼は1週間以上、毎晩「最後の言い訳」を歌っていた。
10年後に明かしたサンタの正体
息子は今、東京で高校生活を送っている。新型コロナウイルスが世界に拡散し、学校も休校になり、親子の会話の時間が増えた。A国で感染者●●人、というニュースを見ながら、息子はその国の友人の名前を口にし、案じている。
続きはこちら